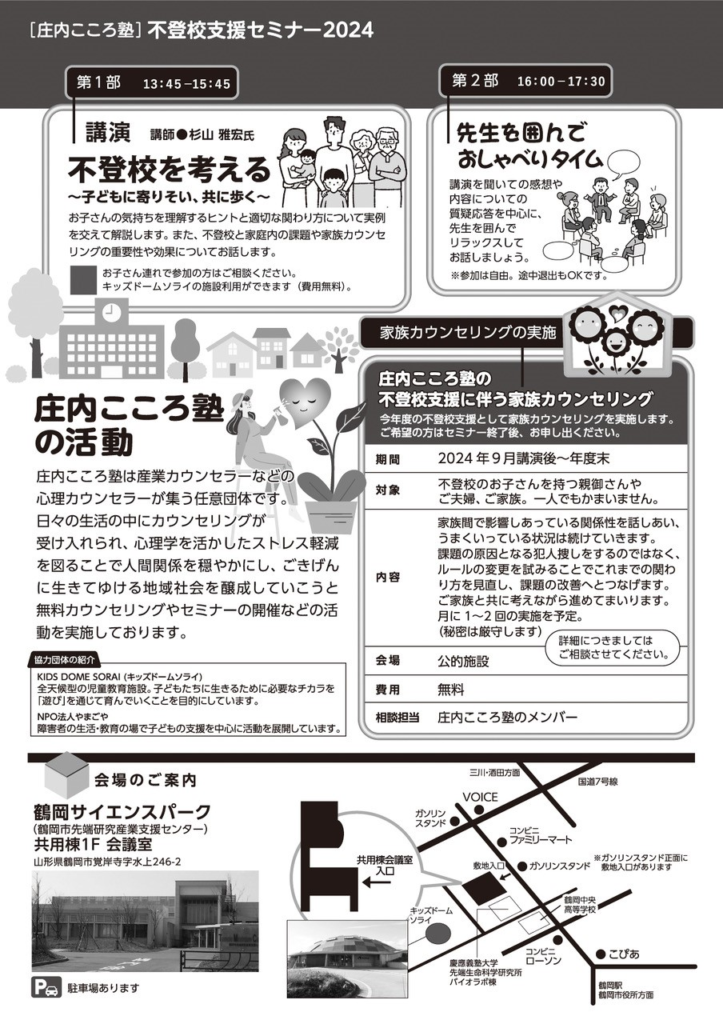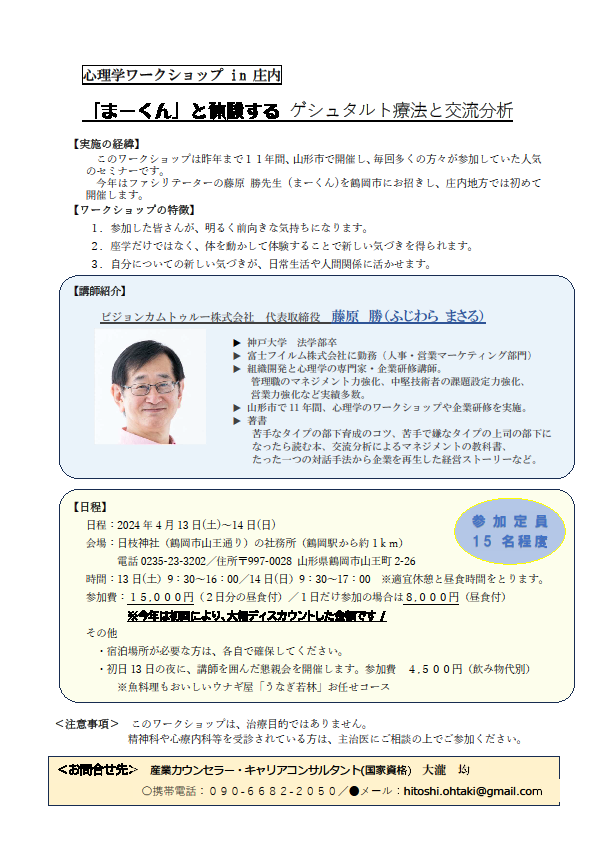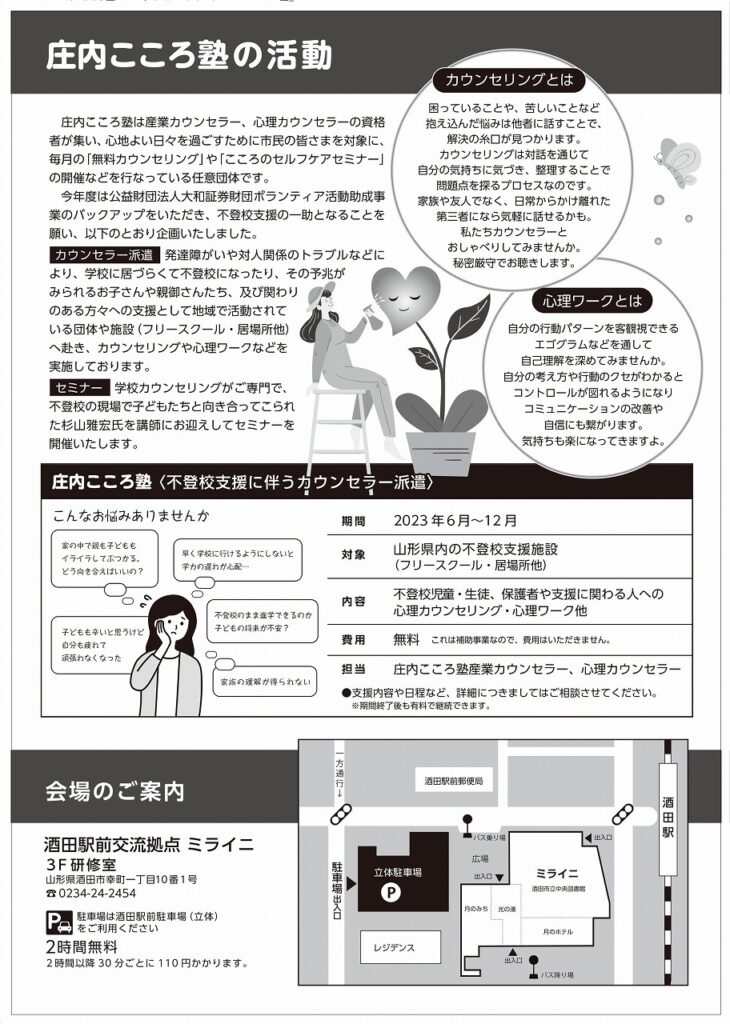育児をしていると、「もっとこうしなきゃ」「完璧な母親じゃなきゃ」と、自分にプレッシャーを感じることってあると思います。私もよく、他の素敵なお母さんと比べて焦ったり、「こんなことでいいのかな?」って悩むことがあります。でも、そんな時に心の中で思い出すのが、ウィニコットの「ほどよい母親」という考え方です。
1. 「ほどよい母親」って、どんな母親?
ウィニコットが言う「ほどよい母親」とは、完璧じゃなくてもいい、という考え方から生まれたものです。例えば、子どもが泣いたときにすぐに抱っこしてあげるのも愛情ですが、時には「少し待ってみようかな?」と思うことも大切。完璧にすべてをこなす必要はなく、母親自身も人間だから、時にはうまくいかないこともあります。
「ほどよい母親」は、子どもの心の声に耳を傾け、愛をしっかり注ぎつつも、過保護になりすぎず、子どもが自分で何かを乗り越える力を育んでいくんです。大事なのは、子どもとのつながりを大切にし、共に学びながら成長していくこと。
2. 完璧を目指すことの難しさと優しさ
育児において「完璧を目指さなきゃ」と感じることは、すごく多いと思います。私もよく、「もっとちゃんとしなきゃ」と思って自己嫌悪に陥ったりしていました。でも、ウィニコットは「完璧な母親」でいる必要はないのだと言っています。
いつも全力で、子どもの欲求に応えようとすると、自分が疲れてしまったり、子どもも「すぐに満たされるのが当たり前」と感じてしまうかもしれません。
時には子どもが自分で待つことを学ぶ機会を与えたり、母親が少し「無理をしている自分」を許してあげることが、子どもの心にとってはとても大切なことです。
3. ほどよい母親でいることが子どもの成長を支える
「ほどよい母親」が子どもの成長にどう関わるのか、少し考えてみましょう。ウィニコットは、母親が時に子どもに全てを与えるのではなく、子どもが自分で何かを乗り越える経験が大切だと言っています。
例えば、子どもが何かで困ったときに、すぐに助けてあげるのではなく、「どうしたら解決できるかな?」と一緒に考えることが、子どもの自信や独立心を育むことに繋がります。もちろん、どうしても辛いときにはすぐに寄り添ってあげることも大事ですが、時には「ほどよく待つ」ことが、子どもにとって大きな力になりえます。
4. 現代の育児とウィニコットの言葉
現代の育児って、情報がたくさんあって、「これが正しい」「こうすべき」というプレッシャーを感じることがよくあります。でも、ウィニコットの「ほどよい母親」という考え方は、無理に完璧を求めるのではなく、愛情を注ぎながら、母親自身もゆっくり成長していけるように背中を押してくれます。
社会が求める「完璧な育児」と自分の実際の育児がギャップがあっても、「ほどよい母親」という考え方を思い出せば、少し気が楽になりますよね。自分に優しくなれる、そんな言葉です。
5. まとめ
「ほどよい母親」って、完璧じゃなくても大丈夫だよ、というウィニコットのメッセージは、育児においてとても大切なことを教えてくれます。愛を注ぎ、子どもの気持ちに寄り添い、時には子どもと一緒に学びながら成長していくことが大切だということ。
完璧な母親でいなくても、あなたの「ほどよい愛情」が、子どもにとって一番大切なものです。完璧を求めず、子どもと一緒に笑ったり、悩んだりしながら、素敵な育児をしていきたいですね。
育児は完璧じゃなくていい、自分も少しずつ成長していけばいいんだというウィニコットの言葉が、母親にとって心強い味方になってくれるはずです。